
この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
「古家の解体費用はどれくらい?売却時にどう影響する?」
結論から言うと、解体費用は建物の構造や広さ、地域によって異なりますが、一般的には60万円〜270万円が相場です。売買のタイミングや契約内容によっては、解体費用を抑えたり、売主・買主のどちらが負担するかを調整できたりする場合もあります。
本記事では、様々な建物の解体工事に携わってきた専門家「あんしん解体業者認定協会」全面監修のもと、古家付き土地の基礎知識や、売買時に押さえておくべきポイントや解体費用相場について解説します。
※本記事では、築20年以上の木造住宅を「古家」と定義しています。
- 古家の解体費用相場(60万~270万円)と、損をしないための内訳の見方
- 「更地渡し」「現況渡し」のどちらが得か、専門家が教える判断基準と失敗例
- 固定資産税が6倍になる前に!知っておくべき税金と法律のリスク
- 相見積もりで30万円安くするコツと、最大300万円の補助金活用術
- アスベスト調査や滅失登記など、罰金を科されないための必須手続き
 監修者
監修者 現場解説
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一(はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
 運営責任者
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
 執筆
執筆「スッキリ解体」専属ライター
馬場 美月(ばば みづき)
「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」
「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。
古家付き土地とは?「更地渡し」と「現況渡し」の違いを解説

まず、古家付き土地とは、古い家が建ったままの状態で売りに出されている土地のことを指します。この古家付き土地を売買する方法には、大きく分けて「更地渡し」と「現況渡し」の2つのパターンがあります。
- 更地渡し:売主が古家を解体し、更地にしてから買主に引き渡す方法です。
- 現況渡し:古家が建ったままの状態で、そのまま買主に引き渡す方法です。
どちらの方法で取引するかによって、解体費用の負担や売却価格、売却までのスケジュールなどが大きく変わってきます。そのため、この違いをきちんと理解しておくことは、売る側・買う側どちらにとっても大切です。
「更地渡し」のメリット・デメリット
↓タブを選択できます↓
売主のメリット
- 買主が見つかりやすい
解体済みのため、買主はすぐに家づくりを始められます。購入検討のハードルが下がり、売却がスムーズに進みやすくなります。 - 契約不適合責任のリスクが減る
建物が残っていると、引き渡し後に雨漏りやシロアリなどの不具合が見つかり、トラブルになることがあります。これを「契約不適合責任」といいます。更地にすれば、こうした建物の不具合による責任を負う心配がほとんどなくなります。
売主のデメリット
- 解体費用がかかる
売主が解体工事を依頼・費用負担する必要があります。家の規模や条件によっては数百万円かかることもあります。 - 解体してもすぐに売れるとは限らない
更地にすれば売りやすくなるイメージがありますが、立地や条件によっては、思ったより売却まで時間がかかるケースもあります。 - 固定資産税が高くなる
建物が残っていると固定資産税が安くなる特例(住宅用地の特例)が使えますが、更地にするとこの特例が外れ、固定資産税が最大6倍になるケースもあります。
「現況渡し」のメリット・デメリット
↓タブを選択できます↓
売主のメリット
- 現況で引き渡せる安心感
古家付きのまま引き渡すため、売却までの流れがシンプルになり、余計な準備に悩まされる心配が減ります。 - 解体費用がかからない
売主自身が解体費用を負担する必要がありません。
売主のデメリット
- 売却価格が下がりやすい
更地よりも買主が見つかりにくく、解体費用や手間を理由に価格交渉されることが多いです。結果として、売却価格が低くなる傾向があります。
古家付き土地の解体費用は誰負担?
「更地渡し」の場合は売主が、「現況渡し」の場合は買主が解体費用を負担するのが一般的です。ただし、契約内容によっては双方の合意により、解体費用の負担を調整するケースもあります。そのため、事前に契約書で負担者を明確にしておくことが重要です。
【初田理事に聞いた】「更地渡し」vs「現況渡し」の判断ポイントとリアルな事例
ここからは解体工事の現場経験と顧客対応の両方に精通し、土地売却に関する相談も数多く手がけてきた『あんしん解体業者認定協会』の初田理事へのインタビューです。「更地渡し」と「現況渡し」のどちらを選ぶべきか迷っている方に向けて、解体のタイミングや売主として知っておきたいリスク、判断のポイントについてアドバイスをいただきました。
 現場解説
現場解説
一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一 (はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
あなたの土地はどちら向き? 判断のカギは「土地の価値」と「売却の目的」
稲垣:率直に伺います。不動産を売却する際、「更地渡し」と「現況渡し」は、どちらが良いのでしょうか?
 理事 初田秀一
理事 初田秀一「高く売りたい」なら更地渡しが有力です。特に都心部など、立地が良くすぐ売れそうな土地なら、先に解体しておくと交渉がスムーズで、高値で売れる可能性が高まります。一方で、「早く手放したい」「ある程度安くてもいい」という場合は、現況渡しで価格を下げて売る戦略も有効です。建売業者などが関心を示すこともあります。

稲垣:なるほど。では、買い手がつくかどうか微妙な立地の土地はどう判断すれば良いのでしょうか?
 理事 初田秀一
理事 初田秀一そうした土地では、まずは現況で売り出して市場の反応を見てみるのが良いと思います。問い合わせがあれば、それは土地に一定のニーズがある証拠ですし、「建物があるから購入に踏み切れない」という声が多ければ、そのタイミングで解体を検討すれば十分です。反応の有無を通じて、その土地のポテンシャルを判断できますよ。

成功例と失敗例に学ぶ売却時の注意点
稲垣:「更地渡し」と「現況渡し」、実際の現場ではどんな成功例や失敗例があるのでしょうか?
 理事 初田秀一
理事 初田秀一はい、印象的だった事例をいくつかご紹介しますね。
成功例:「現況渡し」で高額な解体費用をかけずに売却
 理事 初田秀一
理事 初田秀一「再建築不可」で、しかも火災被害もあった特殊な物件がありました。解体費用が高額で売主様も悩んでいましたが、「現況渡し」で売り出したところ、ある解体業者が「資材置き場として使いたい」と購入してくれたんです。結果的に解体費用を負担せず、手元にお金が残る形で売却できました。
稲垣:個人だけでなく、解体業者が買い取ってくれる場合があるとは驚きです。
失敗例:「更地渡し」で契約が白紙になるリスクも
 理事 初田秀一
理事 初田秀一一方、「更地渡し」には注意が必要です。解体工事の遅れで買主の地盤調査に間に合わなかったり、解体後に地盤の緩みが見つかって売買契約が白紙になるケースもあります。実際、更地にした後に地中から大量のガラ(コンクリート片などの廃材)が見つかり、その撤去に数百万円かかったという相談もありました。
稲垣:高い解体費用をかけても、土地が買い取られなかったり、追加費用がかかったりするリスクも考えておかないといけないんですね。
 理事 初田秀一
理事 初田秀一はい、その通りです。さらに、どちらの渡し方でも「契約不適合責任」を問われる可能性はあります。これは、売買した物件に契約と違う欠陥、たとえば雨漏りや地中の廃材などが見つかった場合に、売主が責任を負う制度です。そのため売却後のトラブルを防ぐには、契約書の内容を細かく確認することがとても大切ですよ。
古家付き土地の税金(固定資産税)と法律

解体後の固定資産税はどうなる?
古家を解体すると、固定資産税が最大で6倍に上がる可能性があります。これは、建物がなくなることで「住宅用地の特例」という税の軽減措置が受けられなくなるためです。
住宅用地の特例とは?

※画像はクリックで拡大できます。
家が建っている土地には、固定資産税が軽減される特例があります。具体的には、土地の200m2までの部分は評価額が6分の1に、200m2を超えた部分は評価額が3分の1に軽減されます。
つまり、古家が建っているだけでも土地の固定資産税はかなり安く抑えられています。
固定資産税の税額は毎年1月1日に決まる
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地と建物の状況を基準に課税されます。たとえば、年末までに解体を終えて「滅失登記(建物が無くなったことの登記)」を済ませた場合、翌年分から更地扱いとなり、税額が上がります。
税金面で有利な売買のタイミングはいつ?
更地を売るなら、年内に売買と引き渡しを終えるのがベストです。固定資産税は毎年1月1日の所有者にかかるため、12月31日までに引き渡せば翌年の税金は買主が払います。年を越すと売主が負担し続けます。
一方で買主は、購入を1月以降にすると税金面で少し得することがあります。1月1日時点で売主が持っていると、その年の税金は売主負担になるため、年明けに引き渡しを受ければ負担が軽くなる可能性があります。ただし、実際は日割り計算で精算するのが一般的です。
特定空き家対策特別措置法とは?
特定空き家対策特別措置法は、自治体が適切に管理されていない空き家を「特定空き家」に指定し、地域の安全・景観・衛生環境を守るために所有者に管理や解体を促す法律です。
「特定空き家」に指定されるのは、次のような空き家です。
- 倒壊の危険がある家
例:柱が傾いている / 土台が腐っている・壊れている - 衛生面で問題がある家
例:悪臭がする / ネズミやハエ・蚊が大量に発生している - 景観を著しく損ねている家
例:屋根や外壁が落書き・汚れだらけ / 敷地にゴミが散乱している - 周囲の生活に悪影響を与えている家
例:枝が道路にはみ出して通行を妨げている/ 誰でも侵入できる状態になっている
特定空き家に指定されるとどうなる?

画像引用:特定空き家とは|NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口
特定空き家に指定されると、自治体から建物の修繕や解体など、状態の改善を求められます。これに従わない場合、次のような3つのペナルティが段階的に課されます。
- 固定資産税の優遇が解除
住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に増額されることがあります。 - 最大50万円の罰金
改善命令に従わなかった場合、最大50万円の罰金が科される可能性があります。 - 行政代執行(強制解体)
空き家の放置が続くと、自治体が強制的に解体を行うことがあります。この費用は所有者の自己負担となり、通常より高額になる傾向があります。さらにこの費用は税金と同じ扱いになるため、支払いを拒むと自宅などが差し押さえられる可能性もあります。
【初田理事に聞いた】空き家解体の「最終警告」が届いた実例
稲垣:法改正のあと、実際に自治体から「空き家を解体してください」といった通知が届いたケースはあったんでしょうか?
 理事 初田秀一
理事 初田秀一はい。以前はほぼゼロだったのですが、今は「放置は許さない」という行政の強い意志を感じますね。とくに衝撃的だったのが、京都のお客様(Bさん)の事例です。
Bさんの元には、ある日突然、役所が撮影したボロボロの実家の写真が添付された通知書が届きました。その内容は、まさに「最終警告」でした。


- 通知日:7月某日
- 期限: 9月1日(約2ヶ月後)
- 要求:期限までに必要な対策を講じること
- 罰則1:従わない場合、所有者の氏名をホームページで公表する
- 罰則2:翌年から固定資産税の優遇措置を解除(税金が最大6倍に)
お客様から「建て替えたいが、すぐには動けない」と役所に相談しても、「待てない」と一蹴されたそうです。これは行政指導の段階でいう「注意→指導→勧告→警告」の最終段階。もはや一切の猶予がない、「末期」の状態でした。
このお客様は、ひとまず氏名公表を避けるため、応急措置として建物をシートで覆う「養生」を行い、その後に解体を進めることになりました。
早めの判断・対策がカギです
老朽化が進んでいる建物をお持ちの方は、できるだけ早めに対策を講じておくことが大切です。とくに売却をお考えであれば、「特定空き家」に指定される前に売却するか、更地にしてから売却することで、税金やトラブルのリスクを軽減できる可能性があります。
 理事 初田秀一
理事 初田秀一「これくらいなら大丈夫」という甘い見通しは通用しません。通知が来てから慌てず、そうなる前の行動が重要です。もし届いたら、無視せずすぐに専門家へ。それが被害を最小限に抑える「最善の初動対応」です。
多くの自治体は「空き家相談窓口」を設けています。気になることがあれば一度相談してみましょう。
古家付き土地の解体費用相場と内訳を解説

古家付き土地の解体費用相場は60万円〜270万円
「あんしん解体業者認定協会」が保有する過去の施工データによると、20坪~40坪の古家の解体費用総額は60万円~270万円が相場です。建物の構造によっても費用は異なり、木造なら60万円~270万円、軽量鉄骨造なら130万円~260万円が目安となります。
「古家」と聞くと、「通常の住宅より費用がかかるのでは?」とご心配される方もいらっしゃいますが、実際にはほとんど差がないことが多いです。
ただし、次のようなケースでは費用が高くなる可能性がありますので、注意が必要です。
費用が高くなる主な要因
- 有害物質を含む建材が使われている
- 老朽化が進み、解体に手間がかかる
- 前面道路が狭く、重機が入りにくい
- 通学路や商店街など人通りが多い
- 庭木や物置など、付帯物の撤去も必要 など
正確な費用を把握するためには、見積もりの際に解体業者に古家の状態をしっかり確認してもらうことが大切です。
古家付き土地の解体費用の内訳
解体工事にかかる費用は、単に建物を壊す費用だけではありません。「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3つの主要な項目で構成されています。

本体工事費
本体工事費は、建物自体を解体するためにかかる費用です。古家付き土地の解体費用全体の約64%を占める、最も大きな費用部分となっています。

具体的には、次のような費用が含まれます。
- 解体作業費
建物を取り壊すためにかかる人件費で、本体工事費の約30%を占めます。 - 廃材の運搬処理費
解体で発生した廃材の処理にかかる費用で、本体工事費の約25%を占めます。 - 仮設養生費
騒音や粉塵対策として建物を覆うシートの設置費用で、本体工事費の約10%を占めます。 - 機械器具および燃料費
重機のリース・燃料費・回送費などで、本体工事費の約10%を占めます。ただし、重機は業者が自社保有していないこともあるため、コストがかさむ場合もあります。 - 解体業者の利益
会社の運営に必要な利益で、各費用に少しずつ上乗せされる形で含まれます。本体工事費の約20~30%を占めます。
とくに「解体作業費」「廃材の運搬処分費」は、坪数・構造・工期・立地などによって大きく変動します。見積もり時には、解体業者に「なぜその金額設定になったのか」を確認することが重要です。
付帯工事費
付帯工事費とは、建物の解体以外で必要な作業にかかる費用です。古家付き土地の解体費用全体においては、約29%を占めるのが一般的です。

具体的には、次のような費用が含まれます。
- 残置物の撤去費
建物内に残っている家具・家電・生活用品などを処分する費用です。 - ブロック塀・門扉・フェンスの撤去費
敷地内のブロック塀や門扉を取り壊し、撤去する費用です。 - 庭木・庭石・植栽の撤去費
庭に植えられている草木や、大きな庭石を処分するための費用です。 - 地中埋設物の撤去費
土地に埋まっている浄化槽・井戸・古い基礎などの撤去費用です。 - アスベスト除去費
建物に含まれる有害物質である「アスベスト」を、安全な方法で撤去するための費用です。アスベストの除去には、専門的な対応が必要となります。 - 地下室・地下車庫の撤去費
地下構造を解体し、埋め戻しを行うための費用です。 - 倉庫・物置・納屋の撤去費
敷地内にある倉庫や物置、納屋を解体・撤去する費用です。 - 駐車場・ガレージ・カーポートの撤去費
敷地内にある駐車場やガレージ、カーポートを解体・撤去する費用です。
付帯工事費は表でご紹介した項目以外にも多くあります。また、敷地内の設備や状況は家ごとに大きく異なるため、付帯工事の内容や費用も現場ごとに変わることをぜひ覚えておきましょう。
諸経費
諸経費とは、本体工事費・付帯工事費に含まれない雑多な費用です。古家付き土地の解体費用全体においては、約7%を占めるのが一般的です。

具体的には、次のような費用が含まれます。
- マニフェストの発行費・管理費
マニフェストは、解体工事で出た廃材がきちんと処分されたことを証明するための大事な書類です。法律で発行と管理が義務づけられているため、その手続きにかかる費用が、見積もりに含まれることがあります。 - 現場管理費
解体工事全体の進行管理や安全管理、作業員の手配などにかかる費用です。 - 保険費
解体工事中に隣家の壁やフェンスを傷つけてしまった場合などに備えて、業者が加入している保険の費用です。 - 近隣対応費
近隣住民への事前挨拶やトラブル防止のための費用(粗品や説明資料の準備などを含む)です。 - 各種申請費
契約書の作成や許可申請、各種書類の管理にかかる費用です。
古家付き土地の見積もり実例
解体費用の目安をより具体的に知るために、実際の見積書の一例をご紹介します。
【静岡県浜松市 築50年】約36坪の木造2階建て住宅

本体工事費:129万1,800円
付帯工事費:24万5,000円
諸経費:6万5,000円
値引き:1万891円
消費税:15万9,091円
→総額は税込175万円です。
詳細を見る
| ▼見積項目一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 見積項目 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 |
| 上物解体(木造2階屋) | 120 | m2 | 8,000 | 960,000 |
| 基礎・土間撤去工事 | 1 | 式 | 115,000 | 115,000 |
| 樹木の伐採・伐根 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 重機回送費 | 2 | 回 | 30,000 | 60,000 |
| 養生架け払い工事(防塵シート) | 196 | m2 | 800 | 156,800 |
| 残置物処分 | 20 | m3 | 10,000 | 200,000 |
| 諸経費 | 1 | 式 | 65,000 | 65,000 |
| 値引き | 1 | 式 | ▲10,891 | ▲10,891 |
| 総額(税込):175万円 | ||||
| ▼見積項目一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 見積項目 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 |
| 上物解体(木造2階屋) | 120 | m2 | 8,000 | 960,000 |
| 基礎・土間撤去工事 | 1 | 式 | 115,000 | 115,000 |
| 樹木の伐採・伐根 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 重機回送費 | 2 | 回 | 30,000 | 60,000 |
| 養生架け払い工事(防塵シート) | 196 | m2 | 800 | 156,800 |
| 残置物処分 | 20 | m3 | 10,000 | 200,000 |
| 諸経費 | 1 | 式 | 65,000 | 65,000 |
| 値引き | 1 | 式 | ▲10,891 | ▲10,891 |
| 総額(税込):175万円 | ||||
古家付き土地の解体費用を抑える方法

複数業者から見積もりを取る
分離発注を決めたら、次に絶対にやっていただきたいのが「相見積もり」です。これは、複数の解体専門業者から見積もりを取り、金額や内容を比較検討すること。
「面倒くさいな」と感じるかもしれませんが、解体費用は業者によって驚くほど金額が異なります。同じ工事内容でも業者によって20万円以上の差がつくことも珍しくありません。
1社だけの見積もりでは、その金額が適正なのかどうか簡単には判断できません。必ず、最低でも3社の解体専門業者から相見積もりを取るようにしてください。これが、適正価格で信頼できる業者を見つけるための最も確実な方法です。
なお、次の記事では、実際に築35年の木造住宅で相見積もりを行い、30万円の費用節約に成功した実例をご紹介しています。
解体時期を調整する
もし工期に余裕があるなら、解体工事の時期を調整することも有効な手段です。
解体業界にも繁忙期と閑散期があります。一般的に、12月~3月は繁忙期にあたります。この時期は業者のスケジュールが埋まりやすく、価格交渉もしにくい傾向にあります。
一方で、比較的工事が少ない4月~9月は閑散期にあたり、業者によっては価格を少し下げてでも仕事を受けたいと考える場合があります。もし可能であれば、こうした時期を狙って交渉してみるのも一つの手と言えるでしょう。

補助金制度を活用する
お住まいの自治体によっては、解体工事に使える補助金や助成金の制度が用意されている場合があります。
ただし、誰でも利用できるわけではありません。補助対象は主に「周辺に危険を及ぼす老朽空き家や付帯物」「アスベスト」などに限定されるケースが多く、単なる建て替え目的では対象外となる可能性も高いのが実情です。
- 老朽危険家屋解体撤去補助金
- 危険ブロック塀等撤去等補助金
- アスベスト対策費助成金
もし対象となれば、工事費用の1/3~1/2程度(上限30~80万円など自治体による)が補助されることもあります。「うちの家は対象外だろう」と決めつけず、まずはお住まいの自治体のホームページを確認するか、担当窓口に問い合わせてみることをお勧めします。
【中野理事に聞いた】補助金申請で失敗しないための重要ポイント
補助金はぜひ活用したい制度ですが、申請でつまずく方も多いと聞きます。ここからは、この記事の監修者で解体に関する法令や制度に精通した専門家である中野理事にお話をうかがいます。
稲垣:中野理事、補助金申請で失敗しないためのポイントを教えてください。
 理事 中野達也
理事 中野達也補助金で最も重要なのは「契約前に申請すること」と「スケジュール管理」です。
多くの自治体では、業者との工事契約後に申請しても対象外となってしまいます。申請でつまずく方が多いのも事実です。特に多いのが、書類の不備や準備の遅れですね。また、自治体によっては予算が決まっており、先着順や抽選で年度の途中で受付が終了してしまうことも珍しくありません。補助金の活用をお考えなら、年度の早い段階から情報収集と準備を始めることが成功のカギですよ。
家の中の不要品は工事前に自分で処分する
家の中の不用品(家具、家電、衣類など)を自分で事前に片付けておくことで、解体費用を大きく節約できます。
解体業者に不用品の処分を依頼する場合、その費用は業者や地域によって異なりますが、一般的には 1m3あたり1万2,000円〜が相場です。たとえば、30坪ほどの家では、5万〜10万円ほどの処分費がかかることも珍しくありません。
手間はかかりますが、リサイクルショップに売ったり、自治体のルールに従って処分したりすることで、余計な出費を確実に抑えることが可能です。
解体業者に値引き交渉する
見積もりを取ったら、値引き交渉も検討しましょう。交渉を成功させるポイントは次の2つです。
- 他社の安い見積書を提示する
「他社では○○万円でした」と伝えることで、値引きに応じてもらいやすくなります。 - 自分が協力できる条件を提示する
例えば、解体費用の一部を先に支払う、工事の時期を解体業者の都合に合わせるなど、解体業者の負担を減らす提案をすると交渉がスムーズです。
複数の解体業者に同時に値引き交渉を行うことは避けましょう。値引き交渉をしたにもかかわらず、最終的に依頼しなかった場合、業者から不誠実と受け取られ、信頼関係を損なう可能性があります。
なお、解体費用の抑え方については次の記事で詳しくご紹介しています。ぜひご参考になさってください。

古家付き土地の解体工事で損をしないための注意点

アスベストの事前調査を行う
まず、解体工事を考える上で避けては通れないのが、有害物質「アスベスト」の有無を調べる事前調査です。2022年4月から法律で厳しく義務付けられており、これはご自身の計画と費用を守るためにも非常に重要なステップです。
この調査は誰でもできるわけではなく、専門の知識と資格を持つ調査員でなければ実施できません。
もし、義務である調査を怠って工事を始めると、作業員や近隣住民の方々に深刻な健康被害を及ぼす可能性があり、100万円以下の罰金が科される可能性もある重大な法令違反となります。
また、「見積もりが安かったから契約したのに、工事が始まってからアスベストが見つかった」というケースも少なくありません。この場合、工事は即中断。そこからアスベスト除去のための特別な作業が必要となり、数十万円以上の追加費用と工期の遅れが発生し、計画が大きく狂ってしまいます。
余計な出費やトラブルを避けるためにも、専門家によるアスベストの事前調査を必ず済ませておきましょう。そのうえで、通常の見積書とは別に「アスベスト込み」の見積書も用意してもらいましょう。
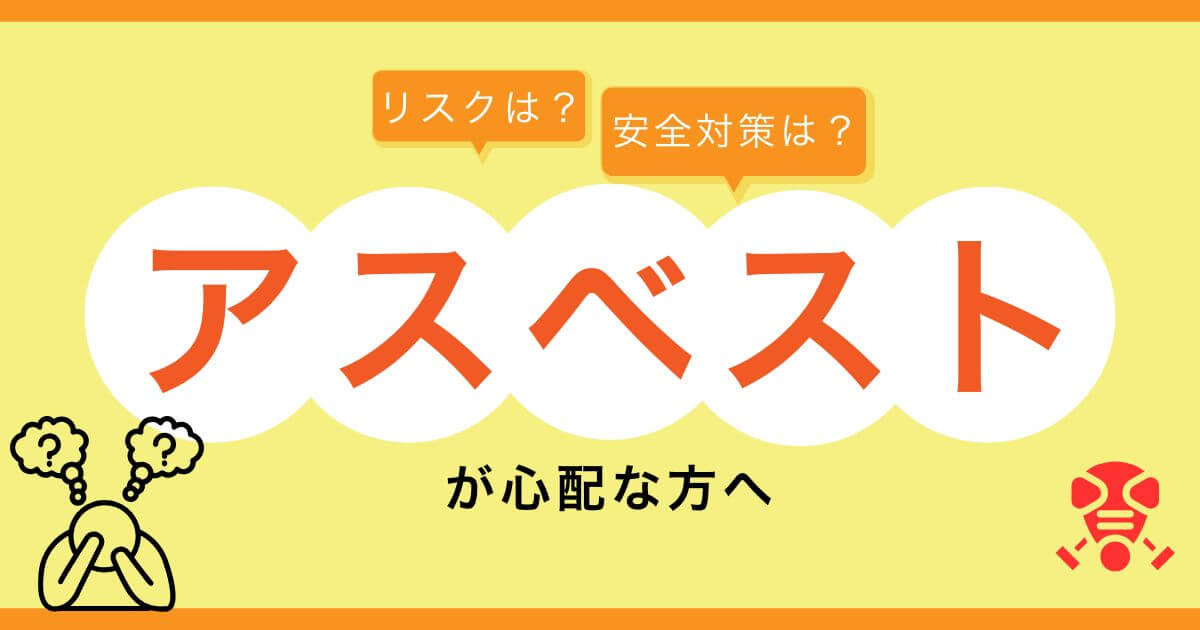
近隣への配慮を怠らない
解体工事中に騒音・粉じん・交通の混雑などで苦情が入ると行政が介入し、工期の遅れや追加費用、最悪の場合は工事中断につながることもあります。
こうしたトラブルを防ぐためには、次の4つの対策をしっかり行ってくれる解体業者を選ぶのがポイントです。
- 事前挨拶
工事前に近隣へ挨拶に行き、工事内容やスケジュール、騒音・粉じんの影響を説明して理解を得ます。 - 騒音対策
作業時間を守り、防音シートを使うなどして騒音をできるだけ抑えます。 - 粉塵対策
水まきや養生シートを使って粉じんの飛散を防ぎ、近隣の健康被害を防止します。 - 交通対策
工事車両の出入りルートや駐車場所を事前に決め、交通渋滞や迷惑駐車を避けます。

工事内容の「認識のズレ」をなくす
業者との「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、工事内容は事前に細かく確認しておくことが重要です。とくに、業者による「現地調査」には必ず立ち会い、次の3点を自分の目と耳で確認しましょう。
施工範囲を確認する
現地調査では、「どこまでを解体するのか」を直接指し示しながら確認することで「壊してほしくないものまで壊された」「残してほしいものが撤去された」といったトラブルを防げます。とくに、隣地との境界にあるブロック塀やフェンスなどは、所有者を明確にしておくことが重要です。
また、家の中に残っている家具や家電(残置物)の量や、庭石、樹木の撤去の有無など、図面だけでは分からない情報を正確に伝えることで、後からの追加費用発生のリスクを最小限に抑えられます。
現場状況(重機の搬入口)を確認する
解体費用を左右するポイント、それは「重機が現場にスムーズに入れるかどうか」です。
解体工事は、ショベルカーなどの重機を使って効率的に進めるのが一般的です。しかし、現場の前の道路が狭かったり、障害物があったりして重機が入れない場合、作業の大部分を手作業で行う「手壊し解体」という方法を取らざるを得ません。
手壊し解体は、重機を使う場合に比べて作業効率が大幅に落ちるため、工期が長引き、その分人件費がかさみます。結果として、解体費用が割高になってしまうことも珍しくありません。
見積もりを依頼する前に、まずはご自身の家の前の道路の幅や、重機が敷地内に入るためのスペースが十分にあるかを確認してみましょう。もし、隣の家の駐車場を一時的に借りることで重機の搬入路を確保できるのであれば、事前に相談しておくことで、費用を大幅に抑えられる可能性があります。
工期を確認する
とくに、解体後に新築や外構工事を予定している場合は、解体工事の開始日と終了日をあらかじめ確認しておくことが大切です。20~40坪の木造住宅を解体する場合、一般的な工期は1~3週間が目安です。
ただし、工期は同じ広さや建物の構造でも現場の状況次第で工期が大きく変わるため、事前の確認が欠かせません。たとえば、道が狭く重機が入れない現場では手作業が必要となり、目安の工期より日数がかかることがあります。
解体工事は天候不良や予想外の追加作業によって、予定より工期が延びることもあります。万が一延びた場合の対応についても、事前に業者へ確認しておくと安心です。多くは契約書に記載されているので、内容をしっかり確認しておきましょう。
解体後に「建物滅失登記」を行う
解体工事が終わったら、基本的に1ヶ月以内に「建物滅失登記」を行い、建物がなくなったことを法務局に届け出る必要があります。もしこの手続きを忘れると、税金を多く請求されたり、10万円以下の罰金が科されることもあります。さらに、土地の売却や建て替えなどのスケジュールにも影響が出る可能性があるので注意が必要です。
申請は法務局の窓口に行く方法と、オンラインで行う方法があります。手続きに不安があれば、土地家屋調査士に代行を依頼することも可能です。
スッキリ解体では滅失登記の申請手続きについて詳しく解説した記事もあります。お困りの方はあわせてご確認ください。

【まとめ】古家付き土地の解体を依頼する前の最終チェックリスト

この記事の要点を踏まえ、最後に確認すべき重要事項をまとめました。一つずつチェックし、万全の準備で次の一歩に進みましょう。
「更地渡し」と「現況渡し」のどちらが自身の状況に適しているか検討します。高く売りたい場合は更地渡し、早く手放したい場合は現況渡しが選択肢となりますが、固定資産税の増加や売却できないリスクも考慮しましょう。
2〜3社以上の解体業者から見積もりを取り、費用を比較検討します。自治体の補助金制度の有無を確認し、不用品を事前に処分しておくことも費用削減につながります。
法律で義務付けられているアスベストの事前調査を必ず実施し、見積もりにその費用が含まれているか確認します。工事完了後は、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請する必要があります。
これらのポイントを着実に実行することが、適切な費用でトラブルなく古家付き土地の解体・売買を完了させることへの最も確実な道筋です。












