
この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
木造住宅の解体を検討する際、多くの方がまず気になるのは「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。特に坪単価の相場は、計画を立てる上での最初の目安になります。
本記事では、解体工事のプロフェッショナルである「あんしん解体業者認定協会」全面監修のもと、木造住宅の詳細な解体費用相場や、木造住宅の解体事例をご紹介します。
- 木造住宅の構造別(平屋、二階建て、三階建て)に解体費用相場を確認できる
- 実際にあった木造住宅の解体事例を確認し、リアルな相場感をイメージできる
- 木造住宅の解体費用が高くなりやすい理由と、その費用を安くする方法がわかる
 監修者
監修者 現場解説
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一(はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
 運営責任者
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
 執筆
執筆「スッキリ解体」専属ライター
酒巻 久未子(さかまき くみこ)
「解体工事でお悩みの方に、同じ主婦の立場から実用的な情報をお届けします。」
数多くのお客様や業者様へのインタビューを通じて、お客様が抱えるリアルな悩みに精通。実際の解体工事現場での取材を重ね、特に「お金」や「近隣トラブル」といった、誰もが不安に思うテーマについて、心に寄り添う記事を執筆。子育て中の母親ならではの、きめ細やかな視点も大切にしている。
木造住宅の解体費用相場

木造住宅全体の解体費用相場
| 木造住宅の解体費用 平均坪単価(全体) | |||
|---|---|---|---|
| 3万4,090円/坪 | |||
木造住宅の解体費用は、1坪あたり3万4,090円が平均的な相場です。これは、階数や特殊な条件を考慮しない全体的な相場です。
| 木造の解体費用 平均坪単価【坪数・地域別】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数/地域 | 関東 | 中部 | 近畿 | 北海道・東北 | 中国・四国 | 九州・沖縄 |
| 10坪 | 4万571円 | 3万8,538円 | 4万7,178円 | 3万7,417円 | 4万723円 | 3万8,718円 |
| 20坪 | 3万6,676円 | 3万3,271円 | 3万8,284円 | 3万7,147円 | 3万6,491円 | 3万1,836円 |
| 30坪 | 3万5,270円 | 3万2,042円 | 3万6,185円 | 3万3,460円 | 2万9,038円 | 3万99円 |
| 40坪 | 3万4,268円 | 3万232円 | 3万5,695円 | 3万2,433円 | 3万3,443円 | 2万8,442円 |
| 50坪 | 3万4,670円 | 3万639円 | 3万4,777円 | 3万3,337円 | 3万2,240円 | 2万8,406円 |
| 60坪 | 3万5,055円 | 3万1,305円 | 3万5,265円 | 3万2,588円 | 3万2,484円 | 3万753円 |
| 70坪 | 3万3,340円 | 3万2,503円 | 3万3,563円 | 3万3,839円 | 3万460円 | 2万7,410円 |
| 80坪 | 3万3,744円 | 2万8,339円 | 3万7,070円 | 2万7,732円 | 3万3,361円 | 2万4,641円 |
| 90坪 | 3万2,643円 | 2万8,147円 | 3万5,662円 | ー | 3万4,095円 | 2万4,575円 |
| 100坪~ | 3万456円 | 2万9,036円 | 3万452円 | 3万297円 | 2万8,790円 | 2万3,866円 |
※解体費用相場は「あんしん解体業者認定協会」が保有する、2020年~2024年の解体工事データ30,000件以上を基に算出しています。
※解体費用相場は平均値です。実際の解体費用は現場の状況や建物の状態によって変動します。
※相場データ内「ー」はデータ不足により算出が出来ない箇所です。
基本的に都心の方が解体費用が高くなり、反対に地方は安くなる傾向があります。これは都心の方が人件費が高くなりやすいこと、建物が密集していることにより狭小地が多くなりやすいことが原因として挙げられます。
狭小地や建物の周囲の道路幅が狭い土地の場合、重機を使った解体作業が制限され、一部手壊しでの解体が発生します。狭い土地でどのように手壊しが行われるかは下記の記事で詳細に説明しています。あわせてご確認ください。

木造住宅 平屋(一階建て)の解体費用相場
木造住宅かつ平屋(一階建て)の平均的な解体費用相場は、1坪あたり3万6,464円です。
以下の表は、さらに詳細な分類である坪数別・地域別に算出した坪単価相場です。
| 木造住宅 平屋の解体費用 平均坪単価 | |||
|---|---|---|---|
| 3万6,464円/坪 | |||
| 木造住宅 平屋の解体費用 平均坪単価【坪数・地域別】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数/地域 | 関東 | 中部 | 近畿 | 北海道・東北 | 中国・四国 | 九州・沖縄 |
| 10坪 | 3万8,209円 | 3万6,085円 | 4万6,964円 | 3万6,652円 | 3万6,195円 | 3万8,268円 |
| 20坪 | 3万4,166円 | 3万1,967円 | 3万9,148円 | 3万8,232円 | 3万8,495円 | 3万1,521円 |
| 30坪 | 3万3,578円 | 3万526円 | 3万7,566円 | 3万3,098円 | 3万3,612円 | 3万775円 |
| 40坪 | 3万2,532円 | 2万8,435円 | 3万6,369円 | 3万1,818円 | 3万3,758円 | 2万8,645円 |
| 50坪 | 3万1,116円 | 2万8,024円 | 3万4,314円 | 3万6,093円 | 3万2,726円 | 3万3,992円 |
| 60坪 | 3万4,096円 | 3万5,719円 | 3万2,420円 | 4万4,951円 | 3万5,912円 | 3万1,332円 |
| 70坪 | 2万8,096円 | 3万4,927円 | 2万9,385円 | 3万5,744円 | ー | 2万5,979円 |
| 80坪 | 3万1,043円 | 2万5,093円 | 3万6,663円 | 3万1,687円 | 2万8,806円 | 2万4,784円 |
| 90坪 | 3万2,590円 | ー | ー | 2万8,352円 | ー | ー |
| 100坪~ | ー | 2万8,174円 | 3万149円 | 2万7,088円 | ー | ー |
※解体費用相場は「あんしん解体業者認定協会」が保有する、2020年~2024年の解体工事データ30,000件以上を基に算出しています。
※解体費用相場は平均値です。実際の解体費用は現場の状況や建物の状態によって変動します。
※相場データ内「ー」はデータ不足により算出が出来ない箇所です。
木造住宅 二階建ての解体費用相場
| 木造住宅 二階建ての解体費用 平均坪単価 | |||
|---|---|---|---|
| 3万6,080円/坪 | |||
木造住宅かつ二階建ての平均的な解体費用相場は、1坪あたり3万6,080円です。
以下の表は、さらに詳細な分類である坪数別・地域別に算出した坪単価相場です。
| 木造住宅 二階建ての解体費用 平均坪単価【坪数・地域別】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪数/地域 | 関東 | 中部 | 近畿 | 北海道・東北 | 中国・四国 | 九州・沖縄 |
| 10坪 | 4万1,715円 | 3万9,531円 | 4万8,297円 | 4万1,424円 | 3万7,234円 | 3万6,239円 |
| 20坪 | 3万7,279円 | 3万4,671円 | 3万8,276円 | 3万5,848円 | 3万5,257円 | 3万2,498円 |
| 30坪 | 3万5,743円 | 3万1,869円 | 3万6,935円 | 3万4,594円 | 3万2,740円 | 3万1,007円 |
| 40坪 | 3万4,564円 | 3万957円 | 3万5,770円 | 3万3,594円 | 3万4,072円 | 3万895円 |
| 50坪 | 3万5,146円 | 3万1,314円 | 3万5,176円 | 3万2,359円 | 3万2,246円 | 2万7,530円 |
| 60坪 | 3万4,840円 | 3万685円 | 3万4,866円 | 3万2,306円 | 3万4,657円 | 2万9,430円 |
| 70坪 | 3万3,991円 | 3万2,656円 | 3万3,965円 | 3万2,868円 | 3万3,374円 | 2万7,391円 |
| 80坪 | 3万3,761円 | 2万7,373円 | 3万5,790円 | 2万7,732円 | 3万1,812円 | 2万5,319円 |
| 90坪 | 3万3,716円 | 2万9,864円 | 3万4,874円 | ー | 3万3,026円 | 2万7,199円 |
| 100坪~ | 3万595円 | 2万7,543円 | 3万537円 | 3万297円 | 2万8,220円 | 2万7,512円 |
※解体費用相場は「あんしん解体業者認定協会」が保有する、2020年~2024年の解体工事データ30,000件以上を基に算出しています。
※解体費用相場は平均値です。実際の解体費用は現場の状況や建物の状態によって変動します。
※相場データ内「ー」はデータ不足により算出が出来ない箇所です。
【初田理事に聞いた】木造の平屋と二階建てはどちらの方が高くなる?
お見せした解体費用相場の一覧表に基づくと、木造の場合は平屋と二階建てに大きな坪単価の差はありませんでした。
この理由を確認すべく、解体工事の専門家である「あんしん解体業者認定協会」の理事として、様々な木造解体の案件に対応してきた解体現場のプロフェッショナル、初田さんに見解を伺いました。
稲垣:木造の平屋と二階建てでは、どちらの方が解体費用は高くなりやすいですか?
 理事 初田秀一
理事 初田秀一一般的には平屋の方が高くなりやすいと言えます。例えば同じ30坪で考えると、二階建てより平屋の方が屋根と基礎の面積が広くなります。解体作業の工程や日数にそこまで違いは出ませんが、屋根の瓦や基礎のガラの処分費用がかさみやすいと言えます。
稲垣:では、坪単価のデータ上で大きな差が開いていないのは何故でしょうか?
 理事 初田秀一
理事 初田秀一二階建ての場合も費用がかさむ要因があるからです。例えば二階部分をはじめに手壊しするケースも多くなり、工数が増えることもあります。また、平屋と比べて狭小地に建てられるケースも多く、解体作業が難しくなるケースも考えられます。
木造住宅 三階建ての解体費用相場
| 木造住宅 三階建ての解体費用 平均坪単価 | |||
|---|---|---|---|
| 4万2,759円/坪 | |||
木造住宅かつ三階建ての平均的な解体費用相場は、1坪あたり4万2,759円です。
以下の表は、さらに詳細な分類である坪数別・地域別に算出した坪単価相場です。
| 木造住宅 三階建ての解体費用 平均坪単価【坪数別】 | |
|---|---|
| 坪数 | 坪単価 |
| 10坪 | 59,246円 |
| 20坪 | 44,473円 |
| 30坪 | 41,809円 |
| 40坪 | 39,566円 |
| 50坪 | 41,625円 |
| 60坪 | 37,654円 |
| 70坪 | 36,448円 |
| 80坪 | 35,217円 |
| 90坪 | 29,425円 |
| 100坪 | 34,219円 |
※解体費用相場は「あんしん解体業者認定協会」が保有する、2020年~2024年の解体工事データ30,000件以上を基に算出しています。
※解体費用相場は平均値です。実際の解体費用は現場の状況や建物の状態によって変動します。
【初田理事に聞いた】木造三階建ての解体費用が高い理由は?
木造住宅の中でも階数別に費用相場を見ていくと、平屋と二階建てには大きな費用差がなく、三階建てから坪単価が高額になっていると分かります。この差にはどのような理由があるのでしょうか?
その理由についても、あんしん解体業者認定協会の初田理事に伺いました。
稲垣:三階建てになると急に坪単価が高額になる印象があります。これはどうしてでしょうか。
 理事 初田秀一
理事 初田秀一建物の階数が高くなると、どうしても手壊し解体が一部発生するケースが多くなり、工事日数が延びやすくなってしまいます。工事日数が多くなると人件費に直結するので、先程の処分費用の差よりも大きなものになりやすいと言えます。
その他 木造の建物別 解体費用相場
その他、木造で建築された建物の解体費用相場は以下です。一緒に取り壊す際の参考になさってください。
| 建物の種類 | 平均坪単価 |
|---|---|
| アパート | 36,333円 |
| 車庫 | 25,660円 |
| 病院 | 38,693円 |
| 倉庫 | 31,469円 |
| 蔵 | 50,857円 |
| 駐車場 | 29,136円 |
| 旅館 | 36,056円 |
| 工場 | 32,736円 |
| 物置 | 19,898円 |
| 店舗 | 36,426円 |
※解体費用相場は「あんしん解体業者認定協会」が保有する、2020年~2024年の解体工事データ30,000件以上を基に算出しています。
※解体費用相場は平均値です。実際の解体費用は現場の状況や建物の状態によって変動します。
木造住宅の解体費用事例
平均的な費用相場を確認したところで、実際に行われた解体事例をもとに、リアルな工事金額を見ていきましょう。
ご紹介する事例は全て「あんしん解体業者認定協会」を通じて行われた実際の解体工事事例です。
【事例1】木造平屋50坪 神奈川県川崎市の事例

| 取り壊した建物 | |
|---|---|
| 構造/種類 | 木造平屋住宅 |
| 棟数 | 2棟 |
| 坪数 | 合計50坪 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区 |

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 単管パイプシート(掛バラシ) | 220 | ㎥ | 800 | 176,000 |
| 重機回送 | 2 | 回 | 20,000 | 40,000 |
| 解体工事 木造平屋建物解体 発生材処分共 | 56.5 | 坪 | 28,000 | 1,582,000 |
| 下屋撤去処分 | 1 | ヶ所 | 20,000 | |
| 土間コンクリート 発生材処分共 | 94 | ㎥ | 3,000 | 282,000 |
| 樹木伐採、抜根、発生材処分共 | 1 | 式 | 80,000 | |
| 【合計】 | 2,180,000 | |||
この解体事例の詳細は以下の記事で確認できます。あわせてご覧ください。

【事例2】木造二階建て30坪 兵庫県川西市の事例

| 取り壊した建物 | |
|---|---|
| 構造/種類 | 木造2階建て/住宅 |
| 坪数 | 約30坪 |
| 所在地 | 兵庫県川西市 |
| 築年数 | ー |

| 品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 足場養生代 | 187.6 | ㎡ | 770 | 144,452 |
| 木造二階部手バラシ解体、処分 | 50.3 | ㎡ | 9,800 | 492,940 |
| 一階部重機併用解体、処分 | 47.6 | ㎡ | 7,400 | 352,240 |
| 門柱、オオヤブロック撤去処分 | 8.3 | ㎡ | 3,800 | 31,540 |
| 同上基礎H450撤去処分 | 11.2 | m | 4,500 | 50,400 |
| カーポート、土間撤去処分 | 1.0 | 式 | 45,000 | 45,000 |
| 諸経費・近隣対策費 | 1.0 | 式 | 15,000 | 15,000 |
| 重機回送費 | 1.0 | 台 | 25,000 | 25,000 |
| お値引 | 1.0 | 式 | -1,572 | -1,572 |
| 消費税 | 92,400 | |||
| 合 計 | 1,247,400 | |||
 理事 初田秀一
理事 初田秀一この事例では建物の二階部分をはじめに手壊しで解体し、その後1階部分を重機で取り壊していることが分かります。二階建ての木造住宅で費用がかさむケースの一例です。
この解体事例の詳細は以下の記事で確認できます。あわせてご覧ください。

【事例3】木造2階建てアパート17坪 東京都世田谷区の事例

| 取り壊した建物 | |
|---|---|
| 構造/種類 | 木造2階建て/アパート |
| 坪数 | 17坪 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 築年数 | 40年 |

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設工事 単管パイプシート(掛バラシ) | 125 | ㎥ | 800 | 100,000 |
| 解体工事 木造2階建物手壊し解体 発生材処分共 | 17 | 坪 | 45,000 | 765,000 |
| 運び出し、積込み手間割増 | 17 | 坪 | 5,000 | 85,000 |
| 残置物撤去処分 | 1 | 式 | 30,000 | |
| 値引き | 1 | 式 | -7,777 | |
| 【合計】 | 972,223 | |||
この解体事例の詳細は以下の記事で確認できます。あわせてご覧ください。

その他にも、スッキリ解体では数多くの木造住宅の解体事例を個別に解説しています。ご自身の建物状況に合った事例がありましたらチェックしてみてください。
横浜市 木造2階建て住宅/横浜市 木造2階建て住宅/鴻巣市 木造2階建て住宅/杉並区 木造2階建て住宅/東村山市 木造2階建て住宅/さいたま市 木造2階建て住宅/さいたま市 木造2階建て住宅/春日部市 木造2階建て住宅/比企郡小川町 木造2階建て店舗兼住宅/横須賀市 木造2階建て住宅/東村山市 木造2階建て住宅/横浜市 木造2階建て住宅/さいたま市 木造2階建て住宅/白岡市 木造2階建て住宅/練馬区 木造2階建て住宅/新宿区 木造2階建て住宅/柏市 木造2階建て住宅/大田区 木造2階建て住宅/鴻巣市 木造2階建て借家/塩谷郡 木造2階建て住宅/坂戸市 木造2階建て住宅/大和市 木造2階建て住宅/川崎市 木造2階建てアパート/横浜市 木造2階建て住宅/
木造住宅の解体費用の内訳【見積書のチェック方法】

見積書の費用の内訳を理解することが、不当な請求や手抜き工事に繋がる見積もりを見抜く第一歩となります。
解体費用は、大きく分けて「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3種類で構成されています。
1. 建物の取り壊しにかかる「本体工事費」

これは解体工事のメインとなる費用で、総額の大部分を占める項目です。具体的には、以下のような作業費用が含まれます。
- 足場と養生の設置:工事中の騒音や粉塵が近隣に飛散するのを防ぐための足場やシートの設置費用です。安全な工事に不可欠なものです。
- 建物本体の解体:重機や手作業で建物の構造体(柱、梁、壁、屋根など)を解体していく作業費用を指します。
- 廃材の分別・搬出:解体で出た木材、コンクリート、金属などを種類ごとに分別し、トラックで処分場まで運ぶ費用です。
- 基礎の撤去:建物を支えていた地面のコンクリート基礎を掘り起こし、撤去する費用となります。
これらの作業が、見積書の中で「木造建物取壊し工事」などと記載されている部分にあたります。

2. 外構や庭石の撤去など「付帯工事費」

付帯工事費とは、建物本体以外にある構造物の撤去にかかる費用です。この項目が見積もりから漏れていると、後から「これは別途費用です」と追加請求される原因になりやすいので、とくに注意が必要です。
現場でよくある付帯工事には以下のようなものがあります。
- ブロック塀、フェンス、門扉の撤去
- 駐車場(カーポート)の撤去
- 庭木や庭石の撤去・処分
- 物置や倉庫の解体
- 浄化槽や井戸の撤去
これらの付帯工事は、見積もりを依頼する際に「どこまで解体してほしいか」を業者に明確に伝えることで、後々のトラブルを回避できます。
3. 書類手続きや人件費などの「諸経費」

諸経費は、工事を円滑に進めるために必要な、現場作業以外のさまざまな費用です。見積書では「雑費」や「管理費」などとまとめられていることもありますが、優良な業者はどこの内訳もきちんと説明してくれます。
主な諸経費には、以下のようなものが含まれます。
- 各種申請手続き費用:建設リサイクル法の届出や、道路使用許可の申請など、役所への手続きにかかる費用です。
- 重機の回送費:解体に使用する重機を現場まで運び、工事後に引き上げるための費用を指します。
- 近隣への挨拶費用:工事前の近隣挨拶で配布する粗品代などが含まれる場合があります。
- 現場管理費・人件費:現場監督の人件費や、工事全体の管理にかかる費用です。
これらの費用が適正に計上されているかを確認することも、信頼できる業者選びの重要なポイントです。
木造住宅の解体費用が高額になるケース【4つのポイント】
木造の建物を解体するにあたって、不測の事態などで費用が高くなってしまうケースを4点ピックアップしてお伝えします。
ケース1:アスベスト調査・除去費用の発生
解体工事を行う前には、有害物質である「アスベスト」の調査が義務付けられています。この調査で建物にアスベストが使われていると判明した場合は、特殊な工法による撤去工事が行われます。
アスベストのレベル、量、場所によって撤去費用は変動しますが、場合よっては数十万円の費用がかかることもあります。
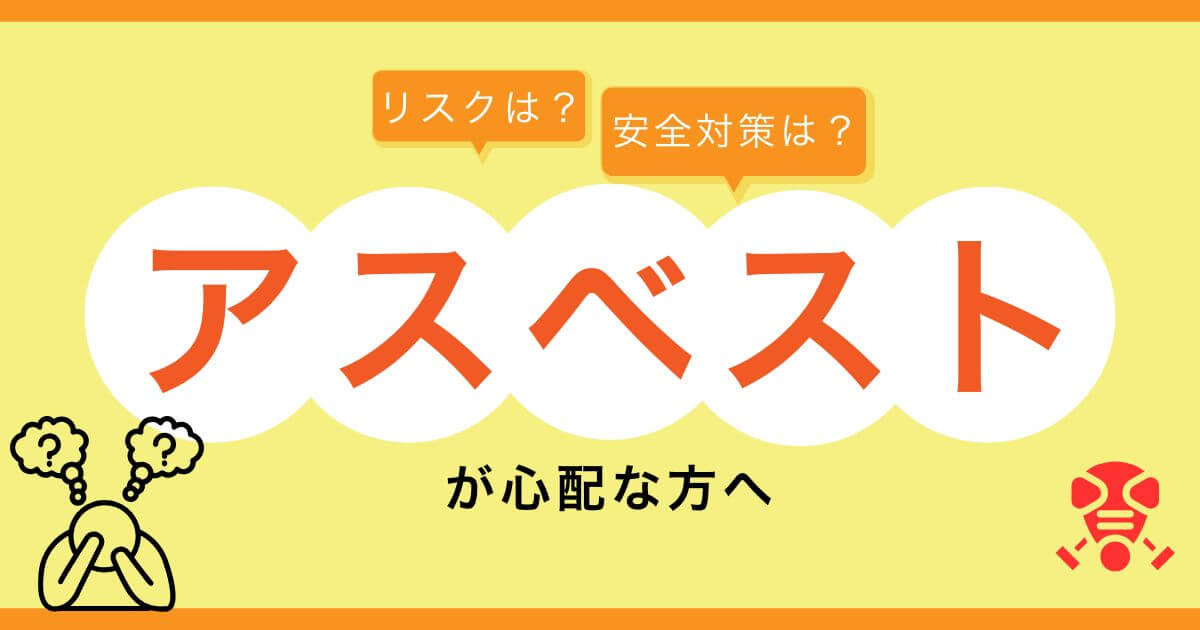
ケース2:地中埋設物による追加費用の発生
解体工事を進めている中で「地中埋設物」が掘り起こされる場合があります。古い建物の基礎(コンクリートガラ)や浄化槽、古井戸などが地中から見つかった場合、撤去作業が必要になります。
これらは当初の見積もりには含まれていないため、発見されると追加費用となり、数十万円単位の高額な請求に繋がることも珍しくありません。
ケース3: 重機が入れない・道が狭いなどの立地条件
立地条件が特殊な場合は費用が高くなる傾向にあります。現場の前の道が狭くて解体用の重機や廃材を運ぶトラックが入れない場合、作業の大部分を手作業で行う「手壊し」解体となります。
また、隣家との距離が近すぎる場合や、隣家が老朽化している場合も手壊し解体になる場合があります。重機を使えば1日で終わる作業が、手壊しだと数日かかることも珍しくありません。その分、人件費が大幅にかさみ、結果として総額が数十万円単位で高くなります。

ケース4: 残置物(不用品)の処分量が多い
家の中に家具や家電、衣類などの不用品(残置物)が多く残っていると、その処分費用が上乗せされます。また、解体業者の見積もり時に「この残置物は処分しておきます」と約束したのに処分していなかった場合、当初の見積もり金額よりも高額になってしまいます。
今回は木造の解体費用が高くなるケースをピックアップしてお伝えしました。専門家の解説を含む、詳細な費用のロジックは以下の記事で網羅的に説明しています。ぜひご確認ください。

木造住宅の解体費用を安くする方法【7つのポイント】
正しい知識を持って行動すれば数十万円単位で費用を安く抑えられるケースがあります。ここでは木造の解体費用を安くするために必要なポイントをピックアップしてお伝えします。
方法1:解体業者の閑散期を狙って依頼する
解体業者の年間スケジュールには閑散期と繁忙期があります。一般的に年末年始や年度末、引っ越しシーズン(12月~3月)は需要が集中するため、繁忙期とされています。
反対に4月~9月は解体業界の閑散期とされており、この時期に工事を依頼することで日程調整の融通が効きやすく、費用を安くできる可能性が高まります。
方法2:自治体の補助金制度を活用する
主に古くなった建物が周囲や景観に被害を与えるのを防ぐため、各自治体は解体工事を促進するための補助金を設けています。
解体工事を計画する際には、事前に「自分の地域で補助金が支給されているか」を調べておきましょう。ネットで検索する際には、「○○市 空き家 補助金」や「○○市 危険ブロック塀 補助金」など、市町村名を入れて検索すると情報を見つけやすくなります。
- 東京都台東区|「台東区老朽建築物等除却工事費用助成金」(最大支給額50万円)
- 福島県郡山市|「郡山市老朽空家除却費補助金」(最大支給額50万円)
- 大阪府岸和田市|「岸和田市不良空家除却事業補助金」(最大支給額80万円)
- 鹿児島県鹿児島市|「鹿児島市危険空家解体工事補助金」(最大支給額30万円)
方法3:必ず3社以上から相見積もりを取る
見積もり依頼は1社だけでなく、3社以上から相見積もりを取りましょう。複数の見積書を比較することで、ご自身のケースにおける費用の適正相場が分かり、不当に高い業者・安すぎて危険な業者を見抜けます。

方法4:家の中の不用品は自分で処分する
家の中にある家具や家電などをなるべく処分しておくと、解体費用を抑えられます。
これらの不用品をそのまま放置した場合は解体業者が処分を請け負うため、その処分費用が見積もりに上乗せされます。
| ▼不用品の処分方法の例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 具体的な品目 | 費用の目安 | 処分方法 | ||
| 日用品 | 可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミ | 基本的に無料 | 自治体のゴミ回収 | |
| 家電製品 | エアコン、洗濯機、冷蔵庫、テレビ | 基本的に無料(売却で収益発生) | フリマアプリやリサイクルショップ | |
| パソコン | ノート型を含むパソコン本体、液晶ディスプレイ | 基本的に無料 | 家電量販店やメーカーの回収サービス | |
| 粗大ゴミ | タンス、布団、机 | 数百円~/点 | 自治体の粗大ゴミ回収 | |
| ▼不用品の処分方法の例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 具体的な品目 | 費用の目安 | 処分方法 | ||
| 日用品 | 可燃ゴミ、 不燃ゴミ、 資源ゴミ | 基本的に無料 | 自治体のゴミ回収 | |
| 家電製品 | エアコン、 洗濯機、 冷蔵庫、 テレビ | 基本的に無料 (売却で収益発生) | フリマアプリ、 リサイクルショップ | |
| パソコン | 本体、 液晶ディスプレイ | 基本的に無料 | 家電量販店、 メーカーの回収サービス | |
| 粗大ゴミ | タンス、 布団、 机 | 数百円~/点 | 自治体の粗大ゴミ回収 | |
残置物の種類や処分について詳しく解説した記事は以下です。
方法5:庭木や雑草を自分で撤去する
敷地内の庭木や雑草の撤去を業者に依頼した場合、1m3あたり9,899円~の費用がかかります。
大きな樹木を切り倒すのは危険ですが、雑草の除去や高さ3m未満・幹の太さ20cm以下ほどの小さな庭木なら、自身で撤去すれば費用を抑えられます。作業の際は軍手をはじめ、安全対策してから取りかかりましょう。
方法6:必要な届け出を自分で行う
解体工事が完了してから1ヶ月以内に、建物滅失登記を届け出る必要があります。
土地家屋調査士に手続きを代行してもらうことも可能ですが、その場合は5万円程度の費用がかかります。自分で手続きをすればその分の費用を抑えられるため、手続きの方法を確認しておきましょう。
なお、スッキリ解体では解体工事後の滅失登記の手続きについて詳細に解説した記事もございます。あわせてご確認ください。

方法7:解体業者に値引き交渉する
解体業者に値引き交渉をするのはマナー違反ではありません。
ただし、複数の解体業者に同時に値引き交渉を行うことは避けましょう。値引き交渉をしたにもかかわらず、最終的に依頼しなかった場合、業者から不誠実と受け取られ、信頼関係を損なう可能性があります。適切な交渉を行うためにも、依頼先を決めたうえで値引き交渉を進めることが重要です。
今回は木造の建物を解体するにあたって効果的な費用の抑え方をピックアップしてご紹介しました。以下の記事では専門家による詳細な解説を含め、費用を安くするための方法をより網羅的に掲載しています。ぜひご確認ください。

木造住宅の解体費用まとめ

本記事では木造住宅の解体費用相場について詳細に解説してまいりました。最後に木造の解体費用のポイントをまとめます。
- 1.木造平屋の解体費用相場
-
木造の平屋住宅は屋根の瓦や基礎のガラの処分費用がかさみやすく、2階建てよりも解体費用が高くなりやすい。
- 2.木造二階建て、三階建ての解体費用相場
-
二階建て、三階建ての木造住宅は一部手壊しになるケースが多く、手壊しになった場合は費用が高くなりやすい。また、狭小地に建てられているケースも多く、解体作業がしづらい場合がある。
- 3.木造ならではの解体費用について
-
他の構造である鉄骨造、RC造と比べると取り壊しやすく費用を抑えやすい。











