
この記事の案内人・編集長
稲垣 瑞稀
- 空き家の解体費用の相場がわかる
- 全国的な空き家の課題と、空き家を放置するリスクがわかる
- 空き家対策にまつわる法律や規制を知り、適切な対処法がわかる
- 空き家の補助金制度の種類と実例がわかる
- 空き家の適切な活用方法がわかる
 監修者
監修者 現場解説
現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一(はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
 運営責任者
運営責任者「スッキリ解体」編集長
稲垣 瑞稀(いながき みずき)
解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。
 執筆
執筆「スッキリ解体」専属ライター
酒巻 久未子(さかまき くみこ)
「解体工事でお悩みの方に、同じ主婦の立場から実用的な情報をお届けします。」
数多くのお客様や業者様へのインタビューを通じて、お客様が抱えるリアルな悩みに精通。実際の解体工事現場での取材を重ね、特に「お金」や「近隣トラブル」といった、誰もが不安に思うテーマについて、心に寄り添う記事を執筆。子育て中の母親ならではの、きめ細やかな視点も大切にしている。
空き家の解体費用相場
まず、ご自身の空き家の費用相場を大まかに掴むことが重要です。解体費用は主に建物の構造によって異なり、坪単価で計算されるのが一般的です。
以下に、構造別の費用相場をまとめました。
| 建物の構造 | 坪単価の目安 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 木造 | 3万4,090円 | 90万円~250万円 |
| 鉄骨造 | 4万9,102円 | 220万円~380万円 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 5万9,169円 | 270万円~420万円 |
※解体費用相場は「あんしん解体業者認定協会」が保有する、2020年~2024年の解体工事データ30,000件以上を基に算出しています。
※解体費用相場は平均値です。実際の解体費用は現場の状況や建物の状態によって変動します。
たとえば、一般的な規模の木造家屋であれば、90万円から250万円程度が目安となります。
もちろん、これはあくまで基本的な建物の解体費用です。立地条件や付帯工事によって金額は変動しますが、まずはこの相場感を頭に入れておきましょう。より詳細な解体費用相場は以下の記事で解説しています。あわせてご確認ください。
空き家問題の現状と放置のリスク

全国的に増え続けている空き家の問題。地方自治体は空き家の所有者に対し、「放置し続けるとリスクがある」と警鐘を鳴らしています。
空き家問題の現状
日本の空き家は年々増加傾向にあります。総務省の調査によると、2023年には過去最多の900万戸に達したと推計され日本の総住宅数に占める空き家の割合は13.8%と、過去最高を記録しました。これは、およそ7軒に1軒が空き家という計算になります。

画像引用:空き家数及び空き家率の推移-全国(1978年~2023年)
そして適切に管理されていない空き家は、以下のようなさまざまな問題を引き起こす原因となります。
- 倒壊のリスク:空き家の腐朽や破損により建物が崩れるリスク。
- 火災のリスク:主に放火による火災のリスク。
- 窃盗や不法投棄のリスク:空き巣や粗大ごみの不法投棄などの犯罪リスク。
- 環境悪化のリスク:害虫・害獣の発生、雑草の繁茂などの環境悪化リスク。
- 景観悪化のリスク:街の景観悪化による行政指導リスク。
倒壊のリスク
老朽化した空き家は、適切な維持管理がされていないため、構造体の腐食や劣化が進行しています。特に、現在の耐震基準(新耐震基準)を満たしていない昭和56年以前の建物が多く、大規模な地震が発生した際に倒壊する危険性が非常に高くなります。
台風や竜巻などの強風によって、屋根瓦やトタン、窓ガラス、外壁などが飛散し、近隣の家屋を損傷させたり、通行人に危害を加えたり、電線を切断して停電を引き起こす可能性があります。倒壊した建物が道路を塞いでしまうと、避難や救助活動、消防活動の大きな妨げとなります。
平成30年度住宅・土地統計調査による「その他空き家」のうち「腐朽・破損あり」(=管理不全):100.6万戸
火災のリスク
消防庁の『令和7年(1月~6月)における火災の概要について』によると、令和7年に起きた火災21,525件のうち、放火(疑いを含む)は2,119件にのぼります。これは全体の出火原因の第1位です。
総出火件数の 21,525 件の出火原因別の内訳は、件数の多い順に、「たき火」1,930 件(9.0%)、「たばこ」1,810 件(8.4%)、「こんろ」1,489 件(6.9%)、「火入れ」1,439 件(6.7%)、「電気機器」1,384 件(6.4%)となっています。
「放火」及び「放火の疑い」を合わせると 2,119 件(9.8%)で、その件数が多い都道府県は、件数の多い順に、東京都 389 件(14.8%4)、神奈川県 183 件(15.2%)、愛知県 172 件(15.2%)、埼玉県 147 件(13.5%)、千葉県 134 件(9.8%)となっています。
空き家は誰も住んでおらず周囲の人目が少ないため、放火のターゲットになりやすいと言えます。
また、消防庁の発表によると、放火の件数の多い都道府県は東京都 389 件(14.8%)、神奈川県 183 件(15.2%)、愛知県 172 件(15.2%)、埼玉県 147 件(13.5%)、千葉県 134 件(9.8%)となっています。
都心部で空き家を所有している方は注意が必要です。
窃盗や不法投棄のリスク
施錠が不完全であったり、窓ガラスが割れていたりする空き家は、容易に侵入できるため、犯罪者の格好の隠れ家となります。盗品の一時保管場所、薬物取引の現場、その他の犯罪の準備場所として悪用されるケースがあります。また、ホームレスなどが無断で住み着く「不法占拠」も発生し、近隣住民とのトラブルに発展することもあります。
しかし、令和4年から2年連続で増加傾向となり、特に、空家に対する窃盗事件の認知件数は、令和3年は173件でしたが、令和5年は、663件と2年間で4倍近く増加と由々しき事態となっております。
また、人目がない空き家の敷地は、家庭ごみから家電、粗大ごみ、さらには産業廃棄物まで、様々なごみの不法投棄場所にされがちです。投棄されたごみは、さらなるごみを呼び込む「割れ窓理論」と同様の状況を生み出し、地域の環境を著しく悪化させます。
環境悪化のリスク
放置された空き家は、ネズミ、ハクビシン、アライグマ、イタチなどの害獣や、ゴキブリ、ハエ、ダニなどの害虫にとって、雨風をしのげる住処・繁殖場所となります。これらの害獣・害虫は、糞尿による悪臭や建物の汚損だけでなく、近隣の住宅にまで侵入し、アレルギーや感染症の原因となる病原菌を媒介するリスクがあります。また、スズメバチが軒下などに巨大な巣を作ることもあり危険です。
また、手入れのされていない庭では、雑草や樹木が生い茂ります。これにより、蚊などの害虫が発生しやすくなるほか、景観を損ないます。繁茂した草木が隣地や道路にはみ出し、通行の妨げや見通しの悪化による交通事故の原因となることもあります。また、浄化槽の管理不全や、不法投棄された生ごみ、動物の死骸などから強烈な悪臭が発生し、周辺住民の生活環境を悪化させかねません。
景観悪化のリスク
外壁の塗装が剥がれ、窓ガラスが割れ、雑草が生い茂り、ごみが散乱した空き家は、それだけで地域の美しい景観を台無しにします。手入れの行き届いた家々が並ぶ中に一軒でも荒廃した空き家があると、街並み全体の印象が著しく悪化します。
例えば歴史ある街並みを保全したいと考える京都市は、全国に先んじて「空き家税(正式名称:非居住住宅利活用促進税)」の導入が決定しました。これは空き家が増えることにより街全体の景観に影響を与えると懸念しているためです。
空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっています。
これらのことを踏まえ、京都市では、非居住住宅の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」を導入することとなりました(課税開始は令和11年度を予定しています)。
また、荒廃した空き家が点在する地域は、「管理が行き届いていない」「治安が悪そう」「住みにくい」といったネガティブなイメージを持たれがちです。これにより、その地域に住みたいと考える人が減少し、結果として土地や建物の資産価値の下落につながる可能性があります。空き家問題が地域全体の経済的な損失を招くことになります。
全国の空き家対策について
各地方自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律に基づいて対策を講じています。空き家を所有されている方はこの法律に基づくルールや規制を把握しておきましょう。
管理不全空家と特定空家
地方自治体は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、管理不十分な状態の空き家を「管理不全空家」や「特定空家」に指定できます。
- 管理不全空家
2023年12月の改正法で設けられた区分。将来的に「特定空家」になる可能性が高いとみなされた管理不十分な空き家を差す。 - 特定空家
放置すると、周辺に直接的な危険や著しい悪影響を及ぼす可能性が高い、非常に深刻な状態の空き家を差す。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等(以下「管理不全空家等」という。)の所有者等に対し、基本指針(第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
自治体が管理不全空家、特定空家に指定した場合は、空き家の所有者に「空き家の適切に管理するように」という通知が届きます。その通知が来ても空き家に改善が見られない場合は、以下の段階で措置が進んでいきます。
- 管理不全空き家(予備軍)に指定 → 勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性がある。
- 特定空家(危険な状態)に指定 → 改善命令に従わなければ、最大50万円の過料(罰金)が科される場合がある。
- 行政代執行(最終手段) → 行政が強制的に建物を解体し、その解体費用全額を所有者に請求する。

画像引用:新たに定義された、「管理不全空家」とは?|NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口
スッキリ解体では行政代執行に至った秋田市のニュースを解説しています。実際の事例としてご確認ください。

【初田理事に聞いた】実際に役所から勧告、指導は来る?
管理不全空き家に関する法改正後、実際に自治体から指導や勧告を受けたという相談は増加しているのでしょうか。ここからは、これまで11万件以上ものお客様の相談に乗り、数多くの空き家を見てきた『あんしん解体業者認定協会』の初田理事に実情を伺います。
 現場解説
現場解説
一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー
初田 秀一 (はつだ しゅういち)
解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。
 理事 初田秀一
理事 初田秀一管理不全空家が指定されるようになってから、行政から通知や勧告を受けたという相談は増えています。
実際に役所や自治体から指導の書類が届いて、「空き家をなんとかしたい」と、慌ててご相談に来られる方が多くいらっしゃいますね。
初田理事によると、行政からの通知が来た方は次のような状況が多いと言います。敷地を越えて他人に被害を与えたり、危険を感じさせたりするような状態になると近隣の方が役所に相談し、それを受けて行政が見に来るという流れが一般的だそうです。
- 庭木が伸び放題になっている
- 外壁が崩れかかっている
- 屋根が落ちている

 理事 初田秀一
理事 初田秀一街でバリケードやカラーコーンが立ててある住宅を見たことはないでしょうか。
「近づいたら危ない」「完全に崩れている」といった状態になると、指導が入ります。
危険度が低い空き家だと、すぐに行政指導に繋がらない場合があります。それよりも、近隣住民の方からの「危ない」「なんとかしてほしい」といった切実な声が、行政が調査に動く直接のきっかけとなる場合が多いです。

空き家バンク
行政は解体の促進だけでなく、「空き家を活用する」方向でもサポートを進めています。代表的なサービスとして、空き家情報を掲載して買い手と繋げる「空き家バンク」があります。
空き家バンクは各市区町村ごとに運営されているものと、全国版として運営されているものがあります。
市区町村の空き家バンク
市区町村ごとに運営されている空き家バンクは、地方自治体のホームページで案内があります。例えば東京都だけでも15の市区町村で空き家バンクが設けられています。
- 参考:としま居住支援バンク|豊島区居住支援協議会
- 参考:国分寺市空き家バンク|国分寺市
- 参考:西東京市空き家バンク|西東京市Web
- 参考:東久留米市空き家バンク|東久留米市
- 参考:調布市空き家バンク|調布市
- 参考:狛江市空き家バンク|狛江市
また、行政では空き家バンクだけでなく「空き家相談窓口」を設けている場合もあります。空き家の解体や活用については全国的に差し迫った問題なため、協力的な体制を敷いている場合がほとんどです。
制度内容は地域によって異なりますので、お住まいの行政のページを確認してみてください。
全国版空き家バンク
全国の物件情報が掲載されている空き家バンクサイトは、平成29年10月より施行運用を開始し、平成30年度より2業者により本格運用を開始しました。
空き家の解体で活用できる補助金
各地方自治体では、空き家対策の一環として解体工事の補助金や助成金を支給しています。取り壊さないと危ないほど老朽化している空き家に関しては、景観維持や地域の安全のために解体を推奨しています。
空き家の解体で活用できる補助金制度は大きく分けて4つあります。
- 老朽危険空き家等除却支援事業
- 特定空き家等除却費補助金
- アスベスト調査・除去費用補助金
- 老朽化した古い家の解体で使える補助金制度
1.老朽危険空き家等除却支援事業
「老朽危険空き家等除却支援事業」は、危険な空き家の解体を考えている所有者にとって、金銭的な負担を大きく軽減してくれる非常に有効な制度です。国(国土交通省)の支援方針に基づき、全国の多くの市区町村(自治体)が、それぞれの地域で実施している補助金制度の一般的な名称です。
そのため、事業の基本的な枠組みは似ていますが、補助金の名称、対象となる建物の細かい条件、補助額、申請期間などは、それぞれの市区町村によって異なります。この事業の主な目的は、個人が所有する危険な空き家を解体(除却)する費用の一部を補助し、地域全体の安全と安心を守ります。「老朽危険」という名前の通り、単なる空き家ではなく、「危険な状態である」と自治体に判定される必要があります。
老朽危険空き家等除却支援事業の条件
老朽危険空き家等除却支援事業の主な条件は以下の通りです。
- 危険性の判定を受けている:自治体職員による現地調査や診断の結果、「不良住宅」や「危険家屋」と判定されたり、法律に基づく「特定空き家」またはその一歩手前の「管理不全空き家」に該当したりする建物。
- 長期間使用されていない:1年以上など、長期間にわたって居住やその他事業などに使われていない状態が客観的に確認できる状態。
- 個人が所有している:法人名義の建物は対象外となる場合が多いです。
- 税金の滞納がない:所有者が固定資産税などの市町村税を滞納していないことが必須条件です。
なお、自治体によって上記の条件や名称が異なる場合があります。自治体のホームページにて対象となる条件を確認しましょう。
【老朽危険空き家等除却支援事業】補助額の計算方法
一般的な補助額の計算方法は、次の計算方法で算出されます。
以下の2つの金額を比べ、いずれか低い方の金額に、定められた補助率を掛け合わせます。
- 実際にかかった解体工事費用(解体業者の見積額・請求額)
- 国や自治体が定めた基準額(建物の延床面積×基準単価などで算出)
その計算結果に対して、自治体が定める上限額が適用されます。
上限額の目安: 50万円〜100万円程度
補助率の目安: 5分の1〜5分の4
2.特定空き家等除却費補助金
「特定空き家等除却費補助金」とは、全国の多くの市区町村(自治体)が実施し、空き家解体のための補助金制度の典型的な名称の一つです。
先述した「老朽危険空き家等除却支援事業」と目的や仕組みは非常によく似ていますが、この制度は「特定空き家」という、法律に基づいて「放置すると非常に危険、または周辺環境に著しい悪影響を及ぼす」と認定された建物を主な対象としている点が特徴です。
そのため、自治体から改善を求める「勧告」や「命令」を受けている空き家が主な対象となります。また名称にある「等」には、特定空き家になる一歩手前の「管理不全空き家」や、自治体が独自に定める基準で「不良住宅」と判定された空き家が含まれる場合があります。
特定空き家等除却費補助金の条件
次のような家の状態であると、「特定空き家」に指定される可能性があります。
- 保安上危険な状態
- 衛生上有害な状態
- 景観を損なう状態
- その他、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態
あくまでも「特定空き家等除却費補助金」の実施主体は市区町村ですので、正式な名称や補助額、条件などの詳細は、空き家のある自治体によって異なります。
【特定空き家等除却費補助金】補助額の計算方法
「実際にかかった解体費用」と「自治体が定めた基準額」を比べ、低い方の金額に定められた補助率(例:2分の1、5分の4など)を掛け合わせ、算出します。そして、その金額には必ず上限額(例:50万円、80万円など)が設定されています。
とくに危険性が高い「特定空き家」を対象とする場合、他の制度よりも補助率が高めに設定されている自治体もあります。
3.アスベスト調査・除去費用補助金
アスベストに関する補助金は、健康被害を引き起こす発がん性物質「アスベスト」の飛散を防ぎ、国民の安全を確保するために設けられた制度です。大きく分けて、以下の2種類の費用が補助対象となります。
- アスベスト調査の補助金(分析調査):ご自身の建物にアスベストが含まれているか、専門の調査機関に依頼して調べるための費用が対象
- アスベスト除去の補助金(除去等工事):調査の結果アスベストがあった場合、それを取り除く(除去)、または飛散しないように固めたり(封じ込め)覆ったり(囲い込み)する工事費用が対象
なお、この補助金は建物の所有者が工事費用を補助してもらうための制度です。アスベストが原因で健康被害に遭われた方が受け取る「給付金」とはまったく別のものですので、ご注意ください。
補助金の対象となる条件は自治体によって異なりますが、一般的には以下のケースが対象となります。
| アスベストに関する補助金の対象となる条件 | |
|---|---|
| 項目 | 主な対象 |
| 対象者 | ・個人の住宅所有者 ・マンションの管理組合(共用部分) ・中小企業の事業者(個人事業主を含む) |
| 対象となる建物 | ・個人が所有する戸建て住宅 ・分譲マンション、賃貸マンション ・事務所、店舗、工場、倉庫など (※多くの場合、大企業が所有する建物は対象外) |
| 対象となる建材 | ・吹付けアスベスト(レベル※1) ・保温材、断熱材など(レベル2) ・屋根材や壁材などの成形板(レベル3) (※自治体によっては、飛散リスクの高いレベル1、2の建材を優先的とする) |
※アスベストのレベル
アスベストの危険性を表していて、飛散性や健康への影響に基づいて「レベル1」「レベル2」「レベル3」の3段階に分類される。レベル1がもっとも危険レベルが高いとされ、解体時には厳重な飛散防止対策が求められる。
アスベストに関する補助金の多くは、解体を目的とせず、今後も利用する建築物を対象としています。ただし、解体工事に伴うアスベスト除去を対象とする補助金制度を設けている自治体もあります。
以下のように、自治体によって補助金の最大支給額が異なります。ぜひ、当てはまる自治体の補助制度を確認しましょう。
- 千葉県千葉市|既存建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(最大支給額100万円)
- 東京都港区|アスベスト対策費助成金(最大支給額200万円)
- 東京都杉並区|解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度(最大支給額5万円)
- 東京都大田区|アスベスト分析調査費助成(最大支給額10万円)
アスベストの概要については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。
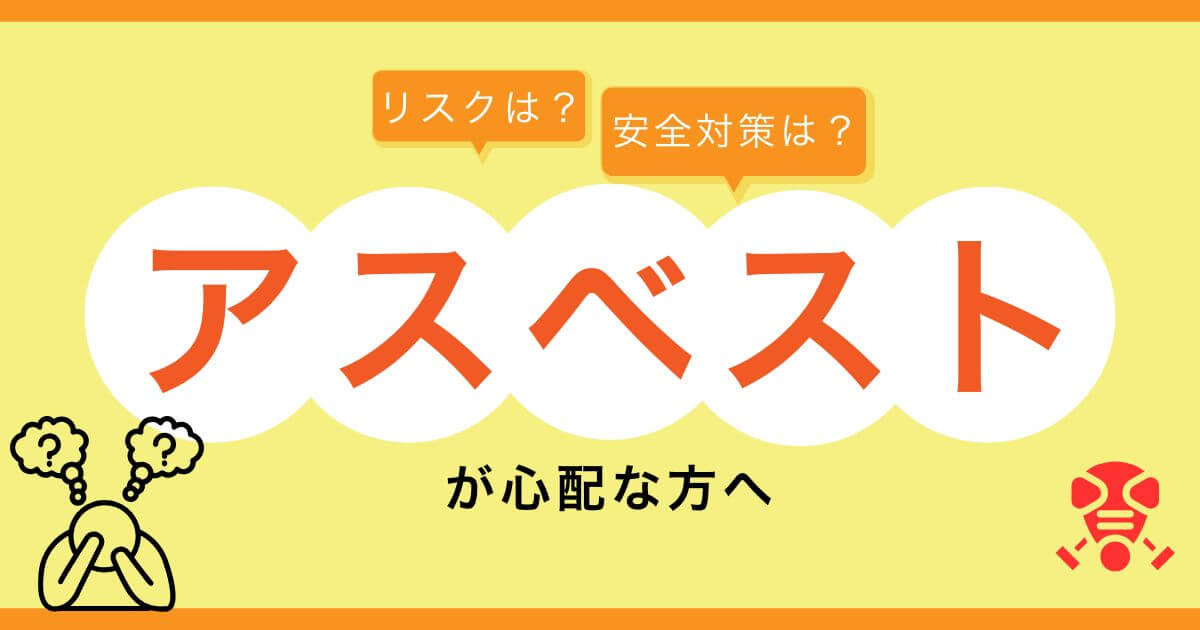
4.老朽化した古い家の解体で使える補助金制度
老朽化した古い家の解体で使える補助金は、「倒壊の危険性がある、または周囲の環境に悪影響を及ぼしている古い空き家などを解体する際に、その費用の一部を市区町村が補助してくれる制度」です。
それには、「老朽危険家屋解体撤去補助金」「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」「建て替え建設費補助金」の3つの補助金制度があります。
| 老朽化した古い家の解体で使える補助金制度の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 補助金の種類 | 主な目的 | 対象行為 | 特徴 |
| 老朽危険家屋解体 | 防災・安全確保 | 解体のみ | 危険と判定された空き家が対象。もっとも一般的。 |
| 都市景観形成地域解体 | 景観の維持・向上 | 解体のみ | 対象エリアが限定される。実施自治体は少なめ。 |
| 建て替え建設費 | 家の性能向上 | 解体+新築 | 新しい家に耐震・省エネ等の性能が求められる。 |
老朽危険家屋解体撤去補助金

老朽化した古い家の解体で使える補助金制度の3つの中でもっとも多くの自治体で実施され、解体を主目的とした基本的な補助金です。
- 対象となる家: 自治体による現地調査で「危険な建物である」と判定された、主に居住者のいない「老朽空き家」が対象。木造住宅の評点基準などを設けている自治体が多い。
- 対象となる行為: 家の「解体」と「撤去」そのものが補助の対象。建て替えの意思がなくても利用可能。
- 補助金額の目安: 解体費用の5分の1~2分の1程度で、上限額は50万円前後が一般的。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
特定のエリアの景観を守ることに特化した補助金です。
歴史的な町並みや条例で定められた景観地区など、地域の美しい景観を損ねている老朽空き家の撤去が目的です。防災よりも「景観」に重きを置いています。
- 対象となる家: 誰でも使えるわけではなく、指定された「景観地区」などにある家のみが対象。
- 対象となる行為:指定エリア内にあり、景観を著しく害していると判断された老朽空き家が対象。
- 補助金額の目安: 解体費用の5分の1~2分の1程度が一般的。
なお都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金は、実施している自治体が少ないため限られます。
また解体後の土地利用については、「景観に配慮した塀を設置する」などの条件が付く場合があります。
建て替え建設費補助金
建て替え建設費補助金は、家の解体とその後の新しい家の建設までをワンセットで支援する補助金です。単に家を壊すだけでなく、耐震性や防火性、省エネ性能の高い家に建て替えにより、より安全で質の高いまちづくりが目的です。
- 対象となる行為: 古い家の「解体」+「高性能な家の新築」がセットで補助対象。解体だけでは利用不可。
- 新築する家への条件: 新しく建てる家には、「現行の耐震基準を満たしている」「燃えにくい構造である」「ZEH(ゼッチ)※などの高い省エネ性能を持つ」といった条件が課せられる。
- 補助金額の目安: 解体費用と建設費用の一部が対象。総額で100万円~数百万円と、他の制度より高額になる傾向がある。
※ZEH(ゼッチ)
Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略。暮らしの中で使うエネルギーを極限まで減らし自らエネルギーを作り出すことで、家全体のエネルギー収支のゼロを目指す住宅。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金は多くの場合、耐震診断が必須となります。
また自治体によって、建て替え後の条件となる性能(耐震、不燃、省エネなど)が異なります。たとえば、大阪市の「建替建設費補助制度」によると、建て替え後の要件には「耐火建築物、準耐火建築物など」とあるため、この通りの設計にする必要があります。
【2025年版】空き家の解体で使える補助金の実例

ここでは、地域別に空き家の解体で使える補助金制度の実例をご紹介いたします。
※記載の情報は、2025年8月時点のものです。
- 東京都台東区|「台東区老朽建築物等除却工事費用助成金」(最大支給額50万円)
- 福島県郡山市|「郡山市老朽空家除却費補助金」(最大支給額50万円)
- 大阪府岸和田市|「岸和田市不良空家除却事業補助金」(最大支給額80万円)
- 鹿児島県鹿児島市|「鹿児島市危険空家解体工事補助金」(最大支給額30万円)
また、以下より全国の空き家対策の実施施策や事例を検索できますので、ぜひご参考になさってください。
 なやみん
なやみんトホホ……自治体のHPで補助金があるか調べてみたけど、「募集受付は終了しました」って書いてあったよ……
補助金の募集の上限に達することは珍しくありません。再度募集される場合もあるので、直接自治体に聞いてみるのがオススメです。
1.東京都台東区の空き家解体補助金事例
台東区では、「台東区老朽建築物等除却工事費用助成金」を設けています。台東区内にある倒壊などの危険性が高いと判断された古い建物を解体(除却)する際に、その工事費用の一部を区が助成してくれる制度です。
まちの安全性を高め、災害に強いまちづくりを目的としています。
| ▼台東区老朽建築物等除却工事費用助成金 | |
|---|---|
| 対象の条件 | ・昭和56年5月31日以前に建築された建築物 ・耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断されたもの ※不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者は除外対象 |
| 申込資格 | ・対象建築物の所有者 ・個人又は中小企業 ・住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税) |
| 支給額 | ・除却費用の3分の1 ・支給額の上限は、50万円 |
| 相談・申請窓口 | 担当課: 台東区役所 都市づくり部 建築課 耐震化推進・建築安全担当 所在地: 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所5階 4番窓口 電話番号: 03-5246-1369 |
申請後に台東区の職員が現地調査を行い、国の「住宅の不良度の測定基準」に基づいて老朽度を判定します。その結果、評点が100点以上(不良住宅)と判断される必要があります。
2.福島県郡山市の空き家解体補助金事例
郡山市では、「郡山市老朽空家除却費補助金」を設けています。郡山市内にある倒壊などの危険性が高いと判断された古い空き家を解体(除却)する際に、その工事費用の一部を市が補助してくれる制度です。
周辺への危害を未然に防ぎ、市民が安全で安心して暮らせる生活環境の確保を目的としています。
| ▼郡山市老朽空家除却費補助金 | |
|---|---|
| 対象の条件 | ・建設業法等の許可を受けた事業者による工事 ・市の交付決定後に契約・着手する工事 ・他の補助金を受けていない工事 ・建物の一部除却、建替え目的でない工事 |
| 申込資格 | ・対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者 (※未登記の場合は、固定資産の登録証明書) ・上記に規定する者の相続人 |
| 支給額 | ・除却費用の2分の1 ・支給額の上限は、50万円 |
| 相談・申請窓口 | 担当課: 郡山市役所 建設部 住宅政策課 所在地: 福島県郡山市朝日4丁目23番7号 郡山市役所 本庁舎2階 電話番号: 024-924-2732 |
郡山市では、補助金の申込みがあった中から予算額の範囲で老朽度合いの高い空き家を優先します。
3.大阪府岸和田市の空き家解体補助金事例
岸和田市では、「岸和田市不良空家除却事業補助金」を設けています。岸和田市内にある老朽化が進み、倒壊などの危険性が高いと判断された空き家を解体(除却)する際に、その工事費用の一部を市が補助してくれる制度です。
管理されていない空き家が原因で起こる事故や防災・衛生・景観上の問題を防ぎ、安全で安心なまちづくりを目的としています。
| ▼岸和田市不良空家除却事業補助金 | |
|---|---|
| 対象の条件 | ・家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れているなど、かなり老朽化したもの ・空家となってから1年以上経つもの ・住宅として居住していたもの ・木造のもの ・空家法による命令を受けていないもの |
| 申込資格 | ・個人である ・市内に所在する不良空家の所有者であり、除却する者である ・本市が賦課する市税を滞納していない ・暴力団員又は暴力団密接関係者でない |
| 支給額 | 1.次のうち低い方の額に延べ面積を乗じた額の8割 ・除却費用を延べ面積で除した額(1平方メートルあたりの単価) ・標準除却費(33,000円/平方メートル) 2.支給額の上限は、80万円 |
| 相談・申請窓口 | 担当課: 岸和田市役所 まちづくり部 住宅政策課 空家対策担当 所在地: 大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所 別館2階 電話番号: 072-423-9562 |
申請後に岸和田市の職員が現地調査を行い、国の「住宅の不良度の測定基準」に基づいて老朽度を判定します。その結果、評点が100点以上(※不良住宅)と判断される必要があります。
4.鹿児島県鹿児島市の空き家解体補助金事例
鹿児島市では、「鹿児島市危険空家解体工事補助金」を設けています。鹿児島市から「特定空家等」として指定されるなど、とくに危険性が高いと判断された空き家を解体する際に、その工事費用の一部を市が補助してくれる制度です。
放置すれば倒壊などのおそれがある危険な空き家を減らし、市民の安全・安心な暮らしの確保を目的としています。
| ▼鹿児島市危険空家解体工事補助金 | |
|---|---|
| 対象の条件 | 1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家である 2.建物が1年以上使用されていない 3.従前の用途が住宅であった 4.下記A、Bのいずれかを満たす A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの |
| 申込資格 | ・空家の所有者又は相続人(法人を除く) ・空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者) ・市税を滞納していない |
| 支給額 | ・除却費用の3分の1 ・支給額の上限は、30万円 |
| 相談・申請窓口 | 担当課: 鹿児島市役所 建築指導課 空家対策係 所在地: 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 東別館3階 電話番号: 099-216-1368 |
鹿児島市の空き家解体の補助金制度は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 「特定空き家」等に認定されている
- 事前調査で、倒壊の危険性が高いと判断される
なお自治体によっては補助金の予算額に達しなかった場合、申込み期間終了後も申込みを受け付ける場合があります。念のため、市役所に一度問い合わせてみましょう。
空き家の活用方法

ここまで解体の重要性をお伝えしてきましたが、解体が唯一の正解とは限りません。あなたの空き家の状態や立地、そしてあなた自身のライフプランによっては、他の選択肢がより良い結果を生むこともあります。
 なやみん
なやみん親が大切にしていた家だから、できれば残したいな……
そんな想いをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。後悔のない決断を下すためにも、解体以外の主な活用法についてご紹介します。

- 「古家付き土地」として現状のまま売却する方法
- リフォームして賃貸物件や民泊として活用する方法
- 更地にして駐車場経営や売却を目指す方法
| 活用法 | メリット | デメリット |
| 古家付き土地売却 | 解体費用がかからない | 売れにくい、売却価格が安くなりがち |
| リフォームして賃貸 | 家賃収入、建物を残せる | 高額なリフォーム費用、空室リスク |
| 更地にして活用 | 管理が楽、売却しやすい | 解体費用、固定資産税増額の可能性 |
「古家付き土地」として現状のまま売却する方法
これは、建物を解体せずに、土地と建物をセットで売却する方法です。最大のメリットは、解体費用がかからないこと。買主側でリフォームや解体を行うため、売主の金銭的負担は少なくて済みます。しかし、建物の状態が悪いと買い手が見つかりにくく、売却価格も土地の価格から解体費用分を差し引いた金額になるのが一般的です。築年数が浅く、状態の良い建物であれば有効な選択肢と言えるでしょう。
リフォームして賃貸物件や民泊として活用する方法
思い出の詰まった家を活かしたい場合に考えられるのが、リフォームして収益物件にする方法です。安定した家賃収入が期待でき、建物を維持管理できるメリットがあります。一方で、数百万円単位のリフォーム費用が必要になるほか、入居者が見つからない空室リスクや、賃貸管理の手間も考慮しなければなりません。とくに、観光地など特定の立地でなければ、民泊としての活用は難しいのが実情です。
更地にして駐車場経営や売却を目指す方法
建物を解体し、更地にした後の活用法です。更地は管理が楽で、売却しやすいという大きなメリットがあります。また、立地が良ければ月極駐車場やコインパーキングとして活用し、安定した収益を得ることも可能です。デメリットは、やはり解体費用がかかることと、前述の通り、土地の固定資産税が高くなる可能性がある点です。
これらの選択肢を比較した上で、あなたの状況にとって何が最善なのかを冷静に判断することが重要です。
【FAQ】空き家の解体に関するよくある質問

行政から指導書が届いたら、まず何をすべきですか?
まずは冷静になることが第一です。
行政からの指導書は、「このまま放置すると、法的な措置を取る可能性がありますよ」という最終警告に近いものです。
最初にやるべきことは、指導書に記載されている内容(何が問題で、いつまでにどうしてほしいのか)を正確に把握し、指定された行政の担当窓口に連絡することです。その上で、「指導に従い、改善に向けて動いています」という意思を明確に伝えましょう。
そして、それと並行して、信頼できる解体業者を探し、見積もりを取る作業を急いでください。誠実に対応する姿勢を見せることが、事態の悪化を防ぐ上でもっとも重要です。
「空き家を解体して更地で売る」のと「古家付き土地として売る」のでは、どちらが手元にお金が残りますか?
古家付き土地のまま売却活動を始め、買主の希望に応じるのがリスクが低いと言えます。
一概にどちらが収益を生むかは断言できませんが、リスク面を考えるなら「先に古家つき土地のまま売却活動をする」方を推奨します。これは「買い手がつかなかった場合のデメリット」が大きいためです。
土地から建物がなくなると軽減税率が外されるため、土地にかかる固定資産税が大きくなってしまいます。そのため買い手がつかない状態で土地を持ち続けるリスクを回避したい場合は、古家つきのまま売りに出した方が良いと言えます。
ただし一般的には更地の方が需要は高いため、売却時の交渉を上手く進める必要があります。
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
行政から届いた通知が「指導」や「助言」レベルでした。すぐに解体しなくてもいいですか?
行政の指示に応じて改善を図ってください。
行政から指導や助言が通知された場合、ただちに解体工事をするとは限りません。例えば敷地内の雑草が生い茂っている場合や、動物や虫が住み着いている場合などは、建物と敷地を綺麗に整え、適切に管理をすればひとまず問題ありません。
ただし建物の老朽化が激しい場合は解体をする必要があります。「どうして通知が来たのか」をよく理解し、適切な対応・管理を心がけてください。
空き家の解体費用に関するまとめ

この記事の要点を踏まえ、最後に確認すべき重要事項をまとめました。一つずつチェックし、万全の準備で次の一歩に進みましょう。
- 1.空き家を放置するリスクと、空き家の法令を理解する
-
ついつい放置してしまいがちな空き家ですが、そのまま放置するリスクや行政の対応を理解することで、空き家解体や空き家活用の一歩目となります。
- 2.空き家の解体費用相場を把握する
-
概算的にでも空き家の解体費用相場を理解することで、解体工事に向けた準備を進められる。
- 3.空き家の活用について検討する
-
空き家を解体して土地を活用するか、空き家そのものを売却・貸借するかを検討する。地方自治体の空き家バンクや相談窓口を利用し、空き家活用に向けた相談を行うのもおすすめ。











